
アフリカドラム村滞在製作記のなか悟空
*スキャナが壊れたため、本文中に写真が表示されない部分が多々あります。いずれスキャナを買ったら挿入します。しばらくお待ち下さい。

<はじめに>
あんれまぁ!こんなヘンピな所まで,ようお越しやす。これは以前リズム&ドラムマガジンに17回にわたって連載されたもんですねん。写真もぎょうさんあるし、旅系の話やドラム作りの話がたっぷりや。ま、ゆっくり読んでいきなされ。
ROUND 1 オイラが旅に出る理由
ROUND 2 アフリカ仕様軽量コンパクト・ドラム の誌上大公開
ROUND 3 ケニヤからウガンダへ
ROUND 4 ついにドラム村に到着
ROUND 5 なーんにも無い村
ROUND 6 ドラム村での暮らし
ROUND 7 子供たちのダンスに衝撃!
ROUND 8 11歳の天才ドラマー
ROUND 9 頭脳を使って翼を生やそう
ROUND 10 民族とリズムに 対する一考察
ROUND 11 無農薬ドラムの製作
ROUND 12 ドラム工房の風景
ROUND 13 ウガンダ製ウス状バス・ドラムの製作
ROUND 14 ウガンダの郵便事情
ROUND 15 土壇場の落とし穴
ROUND 16 世界一のドラムセットの完成
ROUND 17 ファイナル・ステージ
you-tubes
★ウガンダのドラム村での1コマ/約2分 you-tube
http://jp.youtube.com/watch?v=rkjB7N8jXuI
★UGANDA踊る少女たちyou-yube
http://jp.youtube.com/watch?v=mpstZwQpelA
★UGANDA踊る幼女you-tube
http://jp.youtube.com/watch?v=ml91kNu6a78
★UGANDA 生まれて初めてドラム・セットを叩いた少年you-tube
http://jp.youtube.com/watch?v=M7APD-UDYUY
★UGANDA 生まれて初めてドラム・セットを叩いた少年②you-tube
http://jp.youtube.com/watch?v=fhm3gGFWQII
★UGANDAのドラム村での1コマ/約2分youtube
http://jp.youtube.com/watch?v=rkjB7N8jXuI
はじまりはじまりーっ!パチパチ!
ROUND・
1
オイラが旅に出る理由
<ドラムは叩くと---減る>
突然だが---ドラムは叩くと---減る。「そ、そんなアホなァ」
とお思いかも知れないが、実際ドラムは叩くと減ってしまうのである。オイラの言うのは、皮やバチが擦り減るということじゃない。
もっと大切な、肉体のずっとずーっと奥にある、切り刻んでも内視鏡でも見えない「感動」というものが減ってしまうのである。
オイラたちドラマーは、己の肉体とドラムセットと2本のバチを通して、ステージの上で「感動」を切り売りしている。勿論それだけでは決して聴く者の「心」を捕えることは出来ない。それを表現する側の強烈な個性と、表現の裏付けに値する、テクニックとボキャブラリーが無ければ、誰にも相手にされず、マスターベーションで終わってしまう。
「じゃァ、オタクの感動ってナニ?」
ときて当然だろう。人間なんにも感動ナシに生きてるヤツはどこにもいない。増してや人前でバカでかい音で叩きまくろうという、ひときわ目立ちたがりやのドラマー(もしくはこれからドラマーを志す者)だもの。率先して人様(ひとさま)や、バンドのメンバーよりもデッカイものを心の奥に抱いてなけりゃ叩けるわけが無い。
<感動には次元がある>
オイラ達ゃガキじゃねェ。
「えーっ、うっそォー」だとか
「チョー、すっごい」程度のココロのムーブメントでは、感動とは呼ばない。これまで己の生きてきた人生観がひっくり返るほどのショックを---そう、例えばアンディー・フグにカカト落としをくらったような、スタン・ハンセンにウエスタン・ラリアットをくらったようなことを感動と呼ぼう。無論人によってそれぞれ違う。大失恋をしたりだとか、生まれて初めてドラムセットを買ったりだとか、自分の実力以上のドラミングが出来た時だとかもあろう。
チビのオイラは高ゲタを履いて驚いたことがある。これまで自分の見てきた2次元的な世界から、十数センチだけだが3次元の世界が垣間見えたのだ。普段何気なく見てきた日常の世界が、たったその十数センチで違った世界が広がってくる。
また、以前何かの少年マンガで読んだことがある---百メートルを十秒以内で走る人間には、走っている間に「違った世界」が見えるというのだ。バイクや車で走るのとは違う。鍛練に次ぐ鍛練を重ね、それに才能が加味して、選ばれた者にだけ見える世界らしい。
<世界は広いぜよ!>
高ゲタや少年マンガ影響されるところが、いかにもオイラらしく、「しんぷる&すとれーと」だとバンドのメンバーは笑った。言い得て妙だが、ハクナマタタ(スワヒリ語の、気にしない)。
「井の中の蛙、大海を知らず」と言う。
赤城山頂で叩いて富士山に。富士山頂で叩いた後、三千世界に尿(いばり)を放った。
ニッポン列島という、たった4つの小さな島国の中にいて、穴蔵のようなライブハウスで、ポコポコ太鼓を叩くことがなんぼのもんじゃいと、ドラムを担いで海外に漕ぎ出して行った。
天安門広場に万里の長城、チョモランマのベース・キャンプに、キリマンジャロのとっぺん。更にアマゾン放浪、ベトナム、ソマリア難民キャンプ、ウガンダドラム武者修業等々へ、次々にドラムセットを担いで旅立った。これまでよりより高くより広く視野を広げ、更なる3次元ドラマーとなることで、これまでとは「違った」サムシングが網膜に映った。オイラはそれらをむさぼり喰らい、ドラムで叩き出した。
アジア大陸は広かった。
アフリカ大陸は熱かった。
アマゾンは情熱的だった。
否、それだけではない。
幾多の民族とそれに類するだけの音楽、そして音楽に対するそれぞれ価値観。オイラの石頭にもハートにも、ビンビン突き刺さるほどの感動がそこにはある。すぐさまドラムセットを組み立て、それを2本のバチで叩き出す。感性を沸騰させ大汗をかくことで、己自身を発電し充電してきたのだ。
何をどう叩くだとか、どの曲をどんなリズムで、とかいうのではない。心配ご無用!ちっちゃい自分の思惑を超えて、大地の鼓動と人々の眼差しが、身体の中のアドレナリンの分泌を促し、勝手に手足を動かしめるのだ。

ベトナムで吠える/撮影・ベトナム人
<だからオイラは旅に出る>
オイラがドラムを叩く時、虚空を見る。
それはライブハウスのスポットライトでも無ければ、煙草の煙の行方でも無い。
ある時は殺伐とした無限の大地を吹くチベットの風を感じ、またある時は、熱帯のヤシの葉影を照らすザイールの満月を思う。だが旅の途上の悲喜交々と、流した汗と涙に比例する感動もいつしかはかなく薄れ去っていく。 「のどもと過ぎれば熱さを忘れる」の例え通り、悲しいかなどんなに強烈なインバクトも時間と共に消滅していく。
帰国して何十回目かのライブの頃、オイラのバッテリーは点滅を始める。己自身が感動せず、己自身のドラミングにマンネリを感じる時、どうして人に感動を与る事が出来よう。高いチャージを払って来たファンに申し訳ないではないか。悲しいかな作曲の才能の無いオイラにとって、旅の感動をを曲にして残すことも出来ない。「鶴の恩返し」のおつうのように、「感動と言う名の羽」を抜きつつドラムを叩き続けるしかないのだ。
<帰国ライブは醸熟一番絞り>
しょせん人間は手が二本に足が二本、たまに頭やヒジを使ったとしても、そうそう一個人のドラミングが変わるものではない。増してやオイラのように二十年選手が、自分のカラを破るのは、初めてドラムを始めるより難しい。
アフリカへ旅に出て、またアフリカに旅に出て、クソ熱い熱帯のリズムの洗礼を受けて、ホットにホットになってドラムを叩く。醸熟一番絞りを手土産に、己のカラを破れったドラミングを披露するのが楽しみなのだ。
つづく・・・。
ROUND-2
アフリカ用・ 軽量コンパクト・ジャングル仕様の誌上大公開!
<予防注射を7本ブチ込む>
これまでドラムセットを担いだり、リヤカーに積んで引っ張ったりして、アジア大陸横断・アフリカ大陸横断・中南米アマゾンなど、世界中で恐怖の悟空ドラムを叩たきまくってきた。いくら己のパワーを自負していても、アフリカの病気は常軌を逸したものがある。いつものことだが予防注射だけは怠らない。まず黄熱病ーーーこれは1回注射すれば10年は有効だ。そしてA型肝炎ーーーこれはアジアの旅で患って倒れたことがあるので、既に抗体は出来てしまっている。だが破傷風の注射3回と、B型肝炎2回、狂犬病2回(ライオンに食われちゃおしまいだが)は、ブチ込まねばならない。それも一時にやってしまっては人体がもたないので、半年くらいかけて接種する。これで費用が5~6万円はかかるので結構な出費になってしまうので大変だ。おかげで期限切れ食品や少々腐りかけたもの、道端に落ちているものを食べたとしても、なんら健康に異変はない。いま流行のO-157などは、オイラにかかっては単なる調味料でしかない。
マラリヤは現地で調達した予防薬と治療薬をうまく組み合わせて飲めば、かかってもまず死にはすまい。問題はエイズだ。現地でモテモテのオイラが、果たしてアフリカの雌ヒョウどもの誘惑に勝てるのか・・・自信は無い。
なにはともあれ、このたび3度目のアフリカ大陸殴り込み武者修行と相成ったのである。
<ひたすら軽量・防水・防犯・コンパクト>
以前はバスドラムが26インチや22インチのフルセットを担いで出かけたものだが、さすがの悟空もチト疲れちまった。やがて18インチのセットになり、今回は何と16インチのバスドラムを作ってしまった。といってもグレッチのバスタムをバスドラムに改造したのだ!

音色
こそこの雰囲気は獲得できる。いかんせんパワー不足は否めない。
・タム類はピュアカッションの10”+12”+13”にエバンスのオイル入りヘッドで低
音系を、TAMAのティンプ・トム8”+12”には薄めのヘッドで高音系を奏する。
(12”の中に8”がすっぽり要るのがミソ)
スタンド類
用もある。
・タムホルダーやシンバルスタンドの不要部分のカット(イラスト参照)。
製作。
・椅子のスポンジ部分の除去(僅かでもコンパクト化のため)。
・TAMAの13”メタルスネア。
防水 ・TAMAで完璧なのが販売されている。ただしベルトの部分は補強改造してある。以
前は普通のハードケースにペンキを厚めに塗ったり、ロウを塗ったりした。ロウは
熱帯では溶けてベトベトになってしまった。
・ピュアカッションやメタルスネア等、不意のスコールに備えて水に強いものを使用。
・キャスター(写真はバスドラムのケース)
・キャスターが4ケでは引っ張ると転倒しやすいため6ケに。キャスターが大きければ
引っ張りやすいが総重量がかさむし、小さければ 軽いが引っ張りにくい。難しい
ところだ。

防犯
・あちらの犯罪は常軌を逸しているので、食事中やトイレの最中も目が離せな
い。盗られたらドラム旅もパーだ。とにかくチェーンでぐるぐる巻にして、大木
か何かにくくりつけておく。
備品
・スティック2ダース
・全サイズのスペアヘッド
・アウトドア、サバイバル用品
・テント、蚊帳、カメラ、ビデオ、炊事用具、 薬品、ミソ、醤油、梅干し、英・仏辞典
などなど・・・・etc
以上、徹底した軽量化を図っても総重量は70~80Kgにはなる。
※参考資料
軽量・コンパクト化箇条書き
・バスドラム 16”
・スネア 13”
・タム(TAMA) 10”+13”
・ピュアカッション 10”+12”+13”
・シンバル 16”+18”
・HHシンバル 12×12(割れたものをカットして製作)
・シンバルスタンド ジュニアドラム仕様×2
・スネアスタンド なし。TAMAのスターキャスト・マウンティングシステム採用。
・椅子 TAMAのオールドモデルの中から、組立式三脚のものを
使用。クッション部分を除去。
・バスドラム脚 ノーマルを取り外し、ジュニア仕様を取り付け。
・HHスタンド ロジャースのオールドモデルで最軽量のもの。
・フットペダル ラディックのスピードキング。
ROUND-3
ケニアからウガンダへ
<ケニヤでドラムの大御所に会う>
諸君は石川晶という偉大な先逹のドラマーを知っているだろうか? かつて日本の4大ドラマーに、ジョージ川口・猪俣猛・ジミー竹内・ジョージ大塚と言われた時代があった。他のドラマーたちがジャズやポップスに傾倒していった時代、石川氏はジャズのルーツをいち早く看破し、単身アフリカに旅立った。以後「カウントバッファローズ」というアフリカンカラーのバンドを率いて一世を風
靡した。後年の音楽番組「ワンツーどん」の”石川のオジサン”と言えば知ってる人も多いだろう。

往年のテクニックを披露する石川晶氏
以前、オイラはケーキ屋の配達のバイトの最中、車中のラジオで石川氏のコトバを聞いた。「私がタイコを叩く時、リズムの向こうにサバンナの景色が広がる。それはアフリカに行って、アフリカに触れて、アフリカを呼吸した者だけにしか叩けないリズムなのです」。オイラはハンドルを握りながら、不覚にも感極まって大粒の涙を流した。バイトとライブ活動に明け暮れながら、憑かれたように練習をしていたものの、満たされないサムシングを模索していたオイラにとって、このコトバは「天の声」だった。
<ジャパニーズ・アフリカンとは?>
現在、石川氏はケニヤの首都ナイロビで悠々自適の生活をしている。齢60を過ぎ、昨年重病に倒れて半身が多少不自由ではあるが、先日ホームセッションの折に演奏を披露してくれた。左半身が不自由だとは言いながら、ハイハットが3連のウラに的確に入るところは往年のテクニシャンぶりを伺えた。片やオイラはといえば、情けないことに授業参観日の生徒のように、大御所の前では完全に萎縮してしまっていた(プロレスに例えれば、猪木に挑戦する橋本や武藤といったところか)。 氏は言う。「悟空だってアフリカまでドラムセットを担いで来て頑張っているのに、オレも負けてはおれんなァ」。オイラのような鈍才でも、あの石川氏を多少でも啓発できたことがうれしい。
氏はさらに言う。「オレたちにはオレたちの味が有る。アフリカンにはなれないけれど、逆にアフリカンには出せない味が有る。ジャパニーズ・アフリカンとでも言おうかなぁ」。
まるで「あすなろ」の木である。明日は桧(ひのき)になろうと夢見て成長し続ける。永久に桧にはなり得ないけれど、「あすなろ」は夢を見続けることで「あすなろ」の種(キャラクター)が存在する。オイラはあすなろドラマーであってもかまわない。永久に夢を見続けることは、素晴らしい生きざまではないか。<ジャパニーズ・アフリカン>素晴らしい言葉である。氏は現在ケニヤに住む。国籍はジャパンだが正真正銘のアフリカ人である。
<ウガンダへ旅立つ>
ナイロビで国際的に有名な安宿、1泊400円(ツイン)のイクバルホテルで自炊しながら、折々に口実を見つけては石川氏を訪問する。ドラム談義もさることながら、実は美味しい日本食にありつけるからでもある。その日も婦人特製の分厚いトンカツに舌鼓を打ちながら、話題に上ったのがウガンダのドラム村の話。それはドラマーにとってはまるで竜宮城のような、ドラム漬けドラム三昧の千夜一夜物語であった。その話を聞いたオイラは、一も二もなく、リュックを担ぎドラム・ケースを引きづってウガンダへ旅立つことにした。
前号で紹介した通り、オイラのドラム・セットは運搬携帯用コンパクト・アフリカ仕様ではある。だがいくら軽量コンパクトとはいえ、ドラムのケースとスタンドケースで楽に50~60Kgはある。これを両手で引き摺りながら、背中には生活用具とキャンピング用品一式を詰め込んだリュックを背負っている。ウガンダの首都カンパラへは1泊2日のマタツー(乗り合いライトバン)があるが、以前9人乗りに22人詰め込まれたことがある。これではドラムセットが途中で振り落とされるか、強奪されるのが目に見えている。おまけに腹具合でも悪かった日にゃクソもできない。そこで今回はウガンダ国境まで約20時間かかる汽車を選んだ。
ところが汽車といえどもドラム・ケースが大き過ぎて客席に入らない。ケースをデッキにチェーンで括り付けカギを掛けて、不眠で番をするハメになる(それほど盗難が多いのだ)。車窓からは真赤な布を羽織ったマサイ族が牛を放牧させていたり、野性のシマウマがのんびりと草を食んでいるのが見える・・・嗚呼、それもこれもみんなアフリカ、オイラの網膜に焼き付いた全てが、必ずやドラミングに還元されるであろう・・・オイラは大きく息を吸い込んだ。
<カンパラ到着>
国境からはマタツーしかない。しかたなくぎゅうぎゅう詰めの車に乗り込む。ポンコツ車は屋根の荷物をフラつかせながらも、狂ったようなスピードで一路首都カンパラを目指す。狂走と爆塵の果ての3時間後、マタツーはカンパラに到着した。
思えば8年前、この町を初めて訪れた時、アミンの圧政の混乱がまだ覚めやらぬ時期でもあった。ホテルの上下水道は機能せず、外壁には機銃掃射の弾痕が残っていた。しかし時を経た今、遅々とはしているものの、わずかでは有るが復興の兆しが見えた。
その間、我がバンドは4枚のCDをリリースしたものの、オイラのドラミングは決して上達したとは言い難い。さもあらんオイラはうまくなるためにドラムを叩いているのではない。個性的な味付けをさらにドロドロの濃い口にして、そんじょそこらの甘ちゃん音楽ファンが聴くに堪えないようなドラムを叩くのがオイラの天命である(ガハハハハ、CDなんて売れなくてもいいのだ)。
炎天下、直射日光に頭蓋骨を叩き割られるほどの暑さの中、オイラはさらなる己のドラミング改造に決意を新たにした。両拳を固め、肛門を引き締める。
ドラム村は近いぜよ!
ROUND 4
ついにドラム村へ到着
<地図に無い幻の村>
石川晶氏にドラム村を教わりはしたものの、それはあくまで首都のカンパラから車で1~2時間の場所というだけで、方学はまるで分からない。南はビクトリア湖なので、残る東か西か北かのいずれかであろう。
村を探すにしろ村の名前も知らない。
104の番号案内は当然無いし、もちろん電話帳のイエローページも無い。電話ボックスも無ければコインもない(ウガンダにはコインが無いのだ)。オイラは糸の切れたタコのようにさ迷いながら、会う人ごとに訪ねて歩いたが誰も知らない。ドラムを売っている市場の男も、観光案内所のスタッフもどこにあるか知らない。
オイラは焦ってあちこち走り回っていたが、それを知ってか知らずかカンパラの人々の歩高速度は恐ろしく遅い。おそらくナイロビの1/3、東京の1/10程度の速度だろう。これまで訪れた40ケ国の中でも、最ものんびりとしたペースである。中心街が丘の上にあり、歩道があちこち陥没しているせいもあるだろう。それに加え路肩の路上駐車と、てんでばらばらに路上に並んだ露天商、そしてどんなに通行人があろうと辺りはばからず続ける立ち話。それにいつ襲ってくるか分からないスリとかっぱらいの類。さらに赤道直下の炎天下。一日中探し回ると、オイラの肉体も精神もヨレヨレになってしまった。
そんな時、最後に思いついたのが博物館。
博物館へ行けばトラディショナルドラムを展示しているだろうし、係員ならその村の所在を知っているかも知れない。ボロボロのタクシーを使って博物館へ行った。係員は知らなかったが、ドラムを叩く男が週に1回だけ現れるとらしい。それがいつかは分からないが、その男ならドラム村の所在を知っているだろうと言う。オイラは仕方なく連日博物館へ通って、その男の現れるのを待った。 アフリカの旅は待つことから始まる。オイラは中国・チベットの旅で時計の長針を捨て、インドで時計の短針を捨てた。そしてアフリカでは時計そのものが必要なくなってきた。そして“待つ”という観念さえも捨てたとき、初めてアフリカに同化する扉が開けてくるのである。
数日待つとその男は現れた。オイラは石川氏に聞いたムゼー(スワヒリ語で老人の意味)・ガイラの村がどこにあるか尋ねると、男は知っていた。「そりゃァ、ボボーレ村でさァ。ひとつ手前の村が、ダンナの探してるンバンビレっつうドラム村でがすョ」
翌日、男に教えられた通りタクシーパーク(ここでは1ボックスカーをタクシーと呼ぶ)へ向かった。ンバンビレ村には長距離バスは止まらない。それで乗り合いの1ボックスカーで行くしかないのだ。
それにしてもこのタクシーパークは何かと大変だ。甲子園球場ほどの広場に、ハイエースやマイクロバスがぐちゃぐちゃにひしめきあって止まっている。せめて行き先別に分かれていれば車を探しやすいのだが、困ったことにそれぞれの車が自由気ままに客待ちをしているため、行き先はドライバーと車掌にしか分からない。だから人に尋ねてもたいがいは当てにならない。「あっちだ」と教えられた方向へ言ってみたところで、確立は半分だ。
オイラはドラムケースを引っ張り、車のわずかな隙間をすり抜けながら目当ての車を探す。「マサカロード!マサカロード!」まるで迷い子のように声を枯らして叫ぶ。先方は先方で大声で乗客を募っている。そのうち運良くお互いが探し当てれば、次に値段の交渉が始まるのだ。例によってドラムセット持参のため足もとを見られ、けんけんごうごうの交渉が続くのである。
車に乗り込んでからも結構タイヘンだ。
発車時間が決まっているわけではない。ぎゅうぎゅうになるまで乗客を詰め込んで発車するため、ゆうに1時間以上はエアコンの無い車内で待たなければならない。その間、絶え間なく物売りの攻勢にあう。
時計売り、アクセサリー売り、パン売り、コーラ売り、ハンカチ売り、アイスクリーム売り等々が、大声でわざわざ目の前に品物を突き出して勧めるからたまらない。それぞれが1人づつなら数回断れば済むのだが、無数にいるため始末が悪い。それでなくても暑いのだ。「心頭滅却すれば・・・」と目を閉じていてもわざわざ肩を揺すって起こされてしまうのである。思わず「やかましいーっ!」と怒鳴ってしまいたくなるが、「待て待て、ここはアフリカ、エブリシングOKの世界なのだ」と諦める。
そのうち乗客が集まり、ぎゅうぎゅうに詰め込まれた車内で、オイラはどこかのマダムと向き合ったままの姿勢で足を4の字固めのようにもつれさせ、さらに別のマダムがオイラの太股の上に腰掛けたまま車は発車した。悲しいかなオイラの頭は誰かの肘掛けになっているらしく、首を捻らせたままの不自由な態勢になってしまっていたが、少しは窓の外を伺い知れた。
郊外に行くほど緑にあふれ、車はなだらかな丘陵地帯を爆走していた。途中何度か停車しながら小一時間も走った頃、幹線の両側の小屋にオイラは目指すものを発見した。
「マ、マッサーワ!(ここだ!)」オイラは不自然な姿勢のまま叫んだ。
オイラは車の外に躍り出ると、ドラムを引き摺り下ろした。「おおーっ!」目の前の小屋の壁一面に、大小さまざまなドラムがたわわに実っているではないか!
「ほ、ほんまかいなァ・・・」
まるでヘンゼルとグレーテルが、お菓子の家を見つけたように、オイラはドラムの家を見つけたのである。「ゴックン!」思わず生唾を飲み込んだ。

ドラムがたわわに実った家を発見
ROUND-5
な~んにも無い村
<虎穴に入らずんば虎児を得ず>
憧れのドラム村に到着したことで、ぎゅうぎゅうのハイエースの中の酸欠状態からやっと開放されたのはいい。ところがオレンジ色のニッカポッカに安全靴、ヒゲ面と爆発頭にドラムケースという奇妙ないでたちのオイラは、暇そうな村人たちに取り囲まれて質問責めにあってしまった。
「どこの国から来た? 何しに来た? これは何だ? あれは何だ? 髪の毛は本物か? この村に泊まるのか?」ある輩はオイラの髪を引っ張ってみたり、またある輩はドラムのケースをさっそく広げてみようとしたりと気が早い。それを制して今度はオイラが質問をする番だ。「この村に宿はあるか? 米は売ってるか? 野菜はあるか?」--どうやら宿はあるらしい。だが米は無く野菜も無いに等しいと言う。
村人の話によると、この村に泊まりがけで来た観光客はオイラでたったの3人目らしい。数年前アメリカの若い黒人女性が1泊だけして逃げ出したことがあるほか、半年ほど前に日本の大学生が1週間ほどホームステイをしてドラムの作り方を学んだという。この数年内でオイラを含めてたったの3人とは、よくよく旅行者に縁の無い村なのだろう。
以前日本人大学生を泊めた家がホームステイを勧めてくれた。食事付きで一泊約3ドル。一部屋を専用に貸してくれるという。だがここで西欧のホームステイを連想してはいけない。家は土造り、部屋は二畳ほどしかなく窓も無い。ドアの代わりに薄汚れた布きれが垂れ下がっている。食事付きといっても完璧な現地食で、マトーケ、キャッサバ、タロイモ、サツマイモ、チャパティといったお馴染みのエスニックメニューに、ゴキブリやハエが這い回って味付けをしたものである。オイラは彼の好意に感謝しながらも辞退した。
寝る場所が掘っ立て小屋だろうが飯がまずかろうがそれはナントカなる。ドラマーとして最大の問題は「音」だ。
思えば---ドラムを始めた頃から音には苦労をした。アパート、一軒家、どこに住んでも「騒音」を出すオイラは、避難民のようにリヤカーにドラムを乗っけて、河川敷や公園に出けては練習をしていたがそれでも苦情は来た。周辺住民の抗議を受けたり、警察問題になったり、ヤクザにからまれたりしたことも一度や二度ではない。そのたびにオイラのドラミングはスタジオで練習しているドラマーと一線を画し、甲殻類のように強くたくましくなってきたのである。それはともかく、現在は埼玉県の田圃の中でブッ叩いてはいるものの、わざわざウガンダくんだりまで来て「うるさい」と言われたくはない。
そこで、村に一つだけある宿泊者の誰も居ないゲストハウス(?)を根城にすることにした。中庭にテントを張って住めば1泊1ドル。部屋に住めば3ドル。オイラは雨に備えて屋内に住むことにした。1週間後には2ドル伴、2週間後には2ドル、3週間後には1ドル半と、段々とディスカウントしていくように交渉した(だが他の宿泊客が皆無なため、ディスカウントすることに気が引けて、ずっと3ドルのままだった)。
部屋の広さは8畳ほどで、一応ベッドが備え付けてある。持参の蚊帳をベッドに張ると、部屋のまん中にデーンとドラムをセットして、叩きたいときに叩けるように備えた。

ここで24時間ドラム三昧の日々が始まる
<電気・ガス・水道が―――無い!>
夕方になって気付いたが、電気が無い! もちろん電気が無ければ水道も無いのは言わずもがな。ガスだって無かった。まるで吉幾三の歌の文句のような村である。電線が村を通過しているにもかかわらず、電機料金を支払う財力が無いため、村は今だにランプ生活のままなのだ。それでもこういった旅はアフリカの旅では慣れている。それにドラマーにとって必要なのは、電気やガスや水道などの文明の利器ではない。だってドラムの歴史は人類の発生とさほどの違いはない。気が遠くなるほどの遠大なHISTORYがあるのだ。我々ドラマーのDNAに組み込まれた「ドラム遺伝子」は、目先の流行に惑わされることなく、数十万年にわたる歴史に更に数十万年先を見据えるほどのデッカイ夢を抱く必要があるのだ。そのためにもオイラは、西欧文明から隔絶したこの村に腰を据えて滞在し、「伝統とは何ぞや」「ドラムとは何ぞや」を謙虚に学ぶ決意を新たにした。
<出家遁世の朝の始まり>
「コケコッコーッ!」
未明から近所で放し飼いの鶏の鳴き声を皮きりに、鳩や小鳥たちの歌声で朝は何ともすがすがしい。ランプでは読書も出来ず、テレビも電話もステレオも無い長過ぎる夜の闇は、自己の存在を再認識する哲学的な時間ではあるが、その孤独感には堪え難いものがある。長過ぎた夜から開放されたオイラは、生活騒音の皆無なこの村での目覚めに、寒村に出家遁世した俳人のような心地よさを覚える。
さて、例によって朝の体操である。
宿の中庭に出ると、向かいの東の丘に後光がさしている。オイラは愛用のヌンチャクでトレーニングを開始した。剣道のメン・ドウの素振りを何十回か繰り返した後、左右の手で百回づつブンブン振り回し、ブルース・リーのような動きをゆっくりと何度も行なう。このヌンチャクを使った手首のトレーニングは、ドラマーとして必要不可欠なリストの強さと柔軟性を養うための、オイラのオリジナルトレーニング法である。
そうこうしている内に、今日も確実に暑くなるであろう赤道直下のギラギラした太陽が全身を現わす。オイラの額の汗が光る。「よーし、今日もやったるでェーっ!」 ヌンチャクを振り回す腕に一段と力を込めた。

出家遁世のキャンプ生活
ROUND-6
ドラム村での暮らし
<緊急報告! 大バカ者へ乾杯>
オイラがこの連載を開始して半年たったが、ついに読者の中からウガンダへドラムの修業に出かけるという、大バカ者が2人も出現した。
嗚呼!幸いなるかな若き向こう見ず、幸いなるかな若者たち。徳島のY君、北海道のH氏、アフリカ大陸のどまん中でドラムの洗礼を浴びてくるがいい。帰国後の諸君のドラミングが、一皮も二皮もむけていることを期待する。ボンボヤージュ!
<トイレでゴキブリと格闘>

これがトイレ。壁にあるのが紙の変わりの葉っぱ。その右隣はハチの巣。
赤道直下のドラム村で、日の出を睨みつけながらのヌンチャクでの手首のトレーニングを終えると、厠(かわや)に向かう。
板っ切れを打ち付けただけの簡単な戸を明けると、畳の半分ほどの床の真ん中に文庫本ほどの四角い穴が開けてある。尾籠な話で恐縮だが、途上国を旅する上で避けて通れない話なので正直に言おう。ハッキリ言って、命中させるには高等な技術を要する。おまけに紙が無い。どういうわけか後頭部の辺りに木箱があり(とすればオイラは逆向きに座っているのか?)、その中に葉っぱが入れてある。どうやらこれで始末せよということらしい。試しに使ってみたが、この葉っぱの具合のいいことといったらない。まず破れない。しかもウエットティッシュのように湿り気があるというのに、濡れてもいない。オイラはこのクオリティーの高いトイレットペーパー(?)には感動した。 数日後の夜、懐中電灯を持って厠に行って驚いた。ライトに照らし出された三方の壁が、ザザザーッと動いたのだ。あろうことか、その正体はゴキブリであった。だが切羽詰まっていたオイラは所定の位置に座り、両足に這い上がってくる敵サンと悪戦苦闘しながら無事お勤めを果たした。それに懲りて、以後お勤めは必ず明るいうちにすることにした。
<ドラムの修業は水汲みから始まる>
そうこうしているうちに、太陽はギラギラの全身を現わす。今日も間違いなく暑くなることに落胆しながらも、朝の涼しいうちに水汲みに行くことにする。20 入りのポリタンクを持って、ポロンポロン(ウガンダ語でノンビリゆったりのこと)と湧水の出ている窪地に向かう。水は最も貴重である。なんせ20 の水だけで炊事洗濯と洗面、さらに水浴びもしなければならないのだ。

水汲みをする子供達
ここでは幼児でさえも貴重な労働力だ。3~4才の子は5リットルほどのポリタンクで、5~6才で10リットルほどを、7~8才からは20リットルになるのだ。大人の男達は貴重な中国製自家用自転車を活用する。後部サドルに2個乗せて、更に左右に2個吊るし、エンヤコラエンヤコラと押すのである。家から水汲み場まで近いオイラでも往復20~30分、遠い者は小1時間もかかろうか。それでもどの家もおしなべて子沢山なので、水の汲み手には不自由はしない。一家をまかなうだけの水は確保できるようだ。
ポリタンク1杯の水を汲んできたオイラは朝餉の支度にかかる。コッヘルに約2食分の米を入れ、1回だけすすいでキャンピングガスで炊飯開始。洗った水は捨ててはいけない。貴重な水は別の容器にとっておき、野菜を洗ったり手を洗ったりする。更にその後、食後の食器を洗ってやっと捨てるのだ。
ガスの火力を有効に使うため、米を入れたコッヘルの上に味噌汁用のコッヘルを入れて水を温める。主食は米と味噌汁、あとは日本から持参した数種類のフリカケのみ。これを1日2回、連日食べ続けるのである。はっきり言って毎日毎日このメニューでは、かなりキツイものがある。だが間食にフルーツを食べる。子供たちが毎日部屋に持ってきてくれるのだが、砂糖きびやマンゴー、バナナやパパイヤがただ同然の値段で食える。フルーツの女王と言われるジャックフルーツ(ドリアン)でさえ1個30円なのだ。ビールが1本、煙草が一箱それぞれ100円なのを考えると、いかに安価であるか容易に推察できよう。
<ダンス天国の始まり>
食事が終わると、いよいよ大好きなドラムとダンスと合奏の時間が始まる。朝からオイラの部屋につめかけて、箸の上げ下げの一部始終を見ていた子供たちもこの時間を待っている。
彼らにまず持参のハーモニカーとピアニカを渡す。両方とも彼らは初めてである。吹き方もくわえ方も分からない。とりあえず音を出す方法を教える。すると彼らはずーっとメチャクチャに吹き続けている。1人が暫く吹くと、横から誰かがひったくり、そしてまた誰かの手に委ねられ、順繰り順繰りに回し吹きをしている。
オイラは頃合を見計らってピアニカで何曲か吹いてみた。だがだれひとり知ってる曲が無い。村人の殆どがクリスチャンなのを思い出し、賛美歌を少々吹いてみたがこれも反応が無い。それなら、とクリスマスソングを吹いてみたらバカ受け。特に「ジングルベル」と「主は来ませり」である。「ジングルベル」の「♪ミミミー、♪ミミミー」と、「主は来ませり」のイントロ「♪ドーシラソーファ、ミーレードー」が気に入ったらしく、さかんに繰り返している。ハーモニカは目で覚えられないぶん難しいのか、急には無理なようだ。 さて、吹きたい子供らには吹かせといて、オイラはオイラで部屋に備え付けのドラムセットに向かう。すると子供たちはドラムセットの回りに集まってくる。だがオイラは子供たちには気を使わず、己の練習を黙々と開始する。自作のリズムパターンとコンビネーションを何百回も繰り返すのだが、この辺りから踊り子が登場する。ボロボロのスカートをはいているので、辛うじて女の子だと判断できるのだが、宿の隣の6人兄弟の4番目、4才の女の子「ナウケーラ」である。
この子の登場を皮切りに、いよいよ「赤道直下型超エキサイティング・エンドレス・ダンス天国&ドラム地獄」の幕が切って落とされるのである。
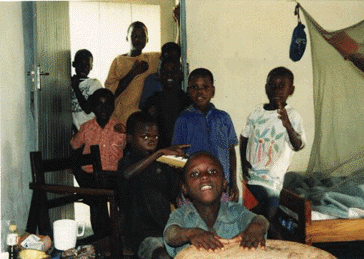

オイラの部屋に連日通って来る好奇心に満ちた少年たち
ROUND-7
子供達のダンスに衝撃!
<アントニオ猪木の闘魂伝承>
炎のカリスマ、アントニオ猪木がついに引退した。長いドラム人生の中でスランプも多々あった。そんな時プロレス会場に足を運び、声を枯らして「猪木コール」を叫んだ。坂本竜馬と植村直己の亡きいま、現世の師匠は猪木氏と石川晶氏しか居ない。
猪木は言った。「人は歩みを止めた時に、そして挑戦を諦めた時に、すでに後退が始まっている」。オイラはブラウン管の前で正座し、号泣しながら拳で涙を拭った。若きドラマー諸君、立ち停まるなかれ! 振り返る無かれ! とにもかくにも猪突猛進あるのみ。道はおのずから出来てくる。我々ドラマーに「引退」の2文字は無いのだ。
プロレスラーであるアントニオ猪木がプロレスだけに固執せず、異種格闘技に挑戦し政界にもチャレンジした。我々がドラマーだからといって、必ずドラムのイスに座らなければならないという理由もないし、両手両足で叩き2本のバチを握らねばならないという鉄則はない。増してやメロディーラインの伴奏を続ける必要も無いし、同じビートを刻み続ける必要はさらさら無い。そういうところから画期的な奏法が誕生するものだ。かつてドラミングの黎明期、型破りなはみだしドラマーたちによって新しいスタイルが生まれてきた。21世紀が近い「今」こそ、我々ドラマーが蜂起する時なのかもしれない。
そのためには、何は無くとも先ず「体力」。頭脳は仕方ないが、ドラム力(力持ちという意味ではない。ドラムを叩く時にどれだけパワーを出せるかということ)をつけることだ。まずスクワットか自転車での暴走。そしてゲンコツでの腕立て伏せと、ヌンチャク。さらに歩きながらでもハンマーを振り回すこと。理想的には自転車で暴走しながらハンマーを振り続けることだろう(オイラは以前、コレで警察に捕まったことがある)。
<赤道直下のダンス天国>
さて話をウガンダに戻す。
宿の隣に自転車の修理屋兼、夕方にはビクトリア湖でとれた魚の頭だけを庭先でフライにして売る魚屋に変身する家がある。そこの6人兄弟(現時点での話。毎年1人づつ生まれ続けている)の4番目、垂らした鼻水のセクシーな ”ナウケーラ”がいる。
4才の彼女はオイラの専属ダンサーである。オイラがドラムの練習を始めるやいなや、立ち上がって腰を振り始める。それはまるで「パブロフの犬」状態だ。人が冷やかそうが声援を送ろうがまるで我関せずで、遠慮がちな視線をオイラに向けながら、ずり下がったボロボロのスカートからヘソを覗かせて腰を振り続けるのである。オイラが演奏をやめない限り踊りをやめない。けっきょく部屋に来ている子供ら全員が連鎖反応で踊り始めるものだから、オイラもノッてしまい、暑くて汗みどろになってもドラムを叩き続けるハメになってしまう。おまけに屋根はトタン板、しかも赤道直下。ホットな演奏を通り越して、焼けるような真昼の大ディスコ大会になってしまうのである。
<ナウケーラの腰振りダンスに関する一考察>
ここでオイラは”腰を振る”という表現を用いているが、”腰を振る”という言葉は”腹が立つ”や”目が座る”と同様、日本語の慣用句であって実際には腰は振らないし腹も絶対立たない。増してや目は座ることは出来ない。恐るべきかな、オイラの経験に照らし合わせると、アフリカ及び中南米諸国の人々のダンスの基本は、”腰を回す”ことから始まる。体の中心線を軸にして、腰だけが独立して別の生き物のようにクルクルと行ったり来たりするのである(ハワイアンダンスともチョット違う)。試しにやってみるといい。決して出来まい。
あの腰の動きがクルッと行って、クルッと返ってくる1セットのコンマ何秒かの中に、オイラたちアジア人や白人たちには未知で不可解な凝縮された音符がぎっしり詰ま
っているのかと思うと、正直いってドラマーとしての自信を喪失しそうになってしまう。

オイラの「専属ダンサー」ナウケーラ(4歳)
<リズムを変えてみた>
悲しいかなオイラは自分の叩くリズムの名前を知らない。もちろんリズムの種類は無数にあり、それを十把(じっぱ)ひとからげにくくって一言で表現することがそもそも無理な話なのだ。というわけでリズムの名前は知らないが、数年前に南米のスリナムで聞いたリズムを叩いてみた(今やっと日本でも流行っているが)。
するとどうだ。彼らの村には電気が無い。当然テレビもビデオもない。ということはニューヨークやロスの黒人ダンサーの踊りなど見たこともないはずなのに。なのにどうして・・・・! お前らいったい何者なんだ。というくらいのカッチョイイのダンスのオンパレード。まるでステンドグラスをぶちまけたような、鋭角的なノリである。オイラは後頭部にアントニオ猪木の延髄切りを食らったような衝撃を受けた。そういえば何年か前、ザイール(現コンゴ民主共和国)の田舎町でマイケル・ジャクソンばりのムーン・ウォークを見て腰を抜かしたこともある。こんなことじゃ彼等が日本に来て踊ったり、2本のバチを持ってドラムを叩いた日にゃ、日本中のダンサーもドラマーも、み~んな失業してしまうわ。えらいこっちゃ。
次回はいよいよ少年達にドラムセットを叩かせてみる話だ。乞うご期待!
<ドラム村のホット情報>
この連載を読んで、先月ンパンビレ村へ行ってきた徳島のY君の報告によれば、村人たちは相変わらずポロンポロン(のんびり)とドラムの製作を続けているとのこと。子供たちは純朴で心を洗われるようだったという。ただ電気の無い村でのローソクの生活は夜が長過ぎたらしい。いずれにせよY君、この村での経験は君のドラム人生の大きな転機になることは間違いあるまい。お互いに目的に向かって歩き続けよう!
ROUND-8
11歳の天才ドラマー
<ウラ拍でジャンプが出来るか?>
オイラは連日、ウガンダのドラム村で赤道直下の大ディスコ大会を催していたが、子供たちのダンスセンスを見て衝撃を受けた。このとき数年前のザイールへのドラム旅を思い出していた。
例によって毎晩のようにディスコ(といっても照明は月明りだけだが)通いをしていたが、このとき彼等のダンスを見ながら重大なことに気がついた。な、なんと!ウラ拍でジャンプをしているのだ。考えてもみよ、オイラたち日本の、いやアジアの農耕民族の伝統的な舞踊の中にジャンプがあるだろうか? さらに小学校に入学以来、単調なラジオ体操で「イーチニーイサーンシー、ニーニサーンシー」とオモテ拍だけで体を動かすように洗脳されてきた。これはある意味では取り返しのつかないほどの”逆義務教育”で、オイラ達は知らぬ間にとんでないリズム教育のハンディキャップを背負わされてしまったことになる。ウソだと思うなら試しにラジオ体操の第一をぜ~んぶウラ拍で試してみるがいい。おそらく出来まい。オンビートだけが無責任に垂れ流され、ウラ拍がカラッポなのに気付くだろう。
蛇足だがジャッキーチェンのカンフーでの立ち回りもそうだ。観察すると彼のアクションはぜ~んぶオモテでジャブやパンチを出している。ということはウラで彼にパンチを打てば、必ずカウンターで入るという理屈になる。それにヒントを得てオイラは数年前に空手を始めた(今月からは剣道も始めるのだ)。慢性的なオンビートドラミングから脱却するためのと、体力&精神力の養成のための一石三鳥的解決策だと思いついたからである。
悲しいかなオイラたちの受けてきた音楽教育と巷間に溢れる音楽は、オンビートだけはライオンのたて髪、オフビートは尻すぼみのハイエナのケツなのである。そういう意味ではネイティブ・アフリカンはオモテもウラもない、いやむしろウラ拍のほうが強調され(オモテとウラだけという単純な問題だけではないが)ている。もしかすると彼等にとっては、我々のいうオモテがウラで、ウラがオモテなのかも知れない。
<ドラムを叩かせてみて驚いた>
オイラの持参したピアニカやハーモニカを子供たちが大喜びで吹きまくっているが、どっこいドラムだけはそういうわけにはいかない。この「携帯用16インチバスドラ・アフリカ仕様6点セット」は製作に数ヶ月を要し、更に埼玉県からウガンダくんだりまでエッチラコッチラ運んできたのだ。そうそう簡単に叩かせてたまるかい。垂涎の的のドラムを叩かせてあげるために条件をジェスチャーで伝えた。「ドラムハタタカセテヤル。ダガ、スティックハジブンデツクッテコイ」。オイラの意志を理解するやいなや、数人の少年が脱兎のごとく外へ駆け出して行った(自分でバチを作ってまで叩きたいという少年を選別する目的がある)。なんせウガンダである。バチになりそうな木はそんじょそこらに生い茂っている。数時間後にはそれぞれが手製のバチを手にして、肩で息をしながらドラムの前に列を作った。
「ヨシ、ユーカラタタイテミロ」。オイラはTAMA製2155P(オーク)を手渡した。いくらなんでも少年たちのこしらえたバチで叩かせるわけにはいかない。文字通り粗削りですぐにヘッドが破れてしまうだろう。
1番、2番、3番バッターの少年たちは、この村のオリジナルのダンスリズム(次回あたりで解説する)を中心にやたらと3連符を叩く。なんせ生まれて初めてドラムセットを演奏するのだ。多くは求めまい。多少のテレや緊張を差し引いたとしても、ドラマーとしての素養は200%ある。
ところがコレで驚いてはいられない。4番バッターにすごい奴が現れた。こやつドラムの椅子に座ると胸の前で十字を切って、いきなりオイラの練習しているリズムパターンをやすやすと叩き始めた(もちろん上半身だけだが)。「おおっ!なんじゃい、このガキゃー!」。これにはオイラも流石に参った。バスドラはとりあえず4拍踏んでいるし、4つあるタム類の移動もぎこちないがやっている。小生意気にも目を閉じて悦に入って演奏している。
少年の名はソーズ。11才。
トラディショナルドラムの演奏は他の子供たちより数段秀でている。もちろんドラムセットは初めての経験だ。彼の一家も他の村人同様ドラムを作っている。オヤジは昼間っから酔っ払ってはいるが、ドラム作りの腕はいい。いちおう小学校には行かせてもらっているらしく、朝は制服を着てはいるが(靴は無く裸足)午後には雑巾のようなシャツに着替えて遊びに来る。
思えば・・・ウガンダに来る前の1年間、浦和市で「闘魂ジャングルドラム道場」を主宰したが、レッスンの開始前に必ず全員でスクワットか拳立てを100回やった。そのため最初は十数人いた門下生も最後はたったの4人だけになってしまった。その4人とも全員がライブ活動をしている現役のドラマーたちだ。弟子達には悪いが、はっきり言ってソーズ君の方に軍杯が上がる。悲しいかな正直言って、オイラもソーズ君のセンスには負けるだろう。

ドラムセットを叩くのは初めてなのに…て,天才じゃあ!
<オイラたちに残されたもの>
止まれ! 若きドラマガの読者諸君。
現実にアフリカの名も無き村に、こういう子供たちが多々いるということはどういうことか。人種の違い。文化の違い。リズム感の違い。彼等は冠婚葬祭もドラムでやる。授業の開始も昼食の合図も全部決まったリズムパターンで知らせる。こんな連中に対抗して我々は一体どうすればいいのか。雲霞の如く存在するアフリカの巨人たちの前で、2本のバチを放り出し敵前逃亡をしてしまうのか。それをやっちゃあおしまいだが、オイラも含めてそれだけでは泣き寝入りが出来ないほどドラムが好きなのだ。
「人間起き上がりこぼし」人はオイラのことをそう呼ぶ。薄暗い揺れるランプの下で、長い夜を泣き明かしてもいられない。蹴られても踏まれても必ず起き上がるダルマのように立ち上がり、逆襲のリズムを叩きつけなければならない。それは猪木イズムであり、開き直った東洋人の感性であり、パワーである。
次回は少年たちのドラミングと門下生のドラミングの根本的な相違について、具体的に分析してみよう。
※番外報告
先日のHIV検査の結果は陰性でした。誌上を借りて報告します。
ROUND-9
頭脳を使って翼を生やそう
<隣村の大御所のもとへレッスンに通う>
オイラの滞在しているウガンダのンバンビレ村、人呼んでドラム村には独特なオリジナルのダンスリズムがある。
このリズムを学ぶために、隣村に住む高名なムゼー(老人の意味)・ガイラ氏のところへ2~3日おきにレッスンに行くことにした。なんせ片道2キロメートルもある。たまに通過する乗り合いタクシーに乗っても20円で行けるのだが、近隣の村人たちは全員歩いているのでオイラだけが贅沢をするわけにもいかない。まァ時間は腐るほどあるのでポロンポロン(ウガンダ語でゆっくりの意味。スワヒリ語ではポレポレ)と滝のような汗を流しながら、黙々と歩いて行くのだ。

ガイラ氏にボンゴを教わるの図。師匠が手にしているのが一弦ハープ
外は晴れ。いつも晴れ。しかも赤道直下の日差しは暴力的なほど熱い。ゴムゾーリの音をペタペタたてながら、なだらかな丘陵の中を行く。たまに隣国ザイールの革命軍を乗せたトラックがオイラの脇を暴走していく。
<トラディショナル・リズム探検>
ガイラ氏が教えてくれたのがこのリズム。
譜面 PCで書き込めないのでゴメンナサイ
この3拍目のアクセントは超がつくほど強力で、太鼓の皮に向かって斜め30度ほどで掌の指先を打ち込むのだから堪らない。しばらく続けていると指先の爪の間から血がにじんでくる。仕方ない。オイラのような小さな掌では、グローブのようなそれを持つ師匠にかなうべくもないのだ。
これを叩くとそばでガイラ氏の3番目の奥さんがシェイカーのオンビートでこう入れる。
譜面
面白いもので6/8拍子好きのオイラには がこう聞こえる。
譜面
そうなるとシェイカーの音はこう聞こえてくる。
譜面
で4分音符が140前後だと、ノッタリとした よりも軽快に聞こえる の方がノリがいい。この方がオイラには素直に乗れてローリング感が出てくる。だが算数的に音符の勘定も合い、小節もズレは全く無いのだが、まるで言葉の通じない彼は暖かい眼差しでオイラをじっと見つめ静かに首を横に振る。どうやら肝心のノリが違うらしい。
それもそうだ。算数的に勘定が合うからといって、日本の盆踊りをレギエのリズムでやったなら、町内会のオバサン達は立ち往生していまうに違いない。しょせん算数は算数、勘定が合うからといってトラディショナル音楽との道程は遠い。
<大御所に関する一考察>
オイラはいつもハーモニカをポケットに入れて歩いているのだが、レッスンの合間に日本の曲やクリスマスソング(ROUND6で触れた)を吹いた。するとどうだ。ガイラ氏は曲名が「むすんでひらいて」であろうが「ジングルベル」であろうが、伴奏のリズムは常に のパターンだけなのだ。8分音符の続くメロディーに3連符のリズムで伴奏するのだから違和感もはなはだしいが、氏はさも楽しそうにノリノリで叩いている。
今度は師匠が1弦ハープをデタラメ?に弾きまくる。このハープは、くの字型の木に弦を1本だけ張ったものを、牛の尾で作った弓で弾くのだが、フレットは無く押さえたとこ勝負のメロディーが出る。弓を持つ右手の往復運動のしかた次第で、かなりリズミックな演奏ができるので面白い。それに対しオイラはタイコで16分音符のサンバ系リズムで伴奏する。すると師匠、自分の年も忘れて弾きまくるのである。
以上のことからガイラ師匠は、自分がタイコを叩く時はあくまで自分のスタイルで演奏し、聞く側または伴奏される側に立ったときは、許容範囲が広いと結論付けることができる。
<セッションで発見したもの>
ところでオイラの部屋では連日のディスコ大会やドラム道場に加え、オイラのドラムセット対トラディショナルのドラムセッションもやっていた。村人たちのほとんどがドラム職人でありドラマーでもあるとは言ったものの、中にはドラムは作るが演奏はまるでダメ者や、演奏してもリズム音痴な奴もほんの僅かだが居た。その者たちは別として、ドラム演奏の上手な若者たちの中にも2種類のプレヤーが存在することがわかった。
ひとつはオイラのジャズ的(ある意味では算数的とも言える)なドラミングに対し、頑(かたく)なに伝統的な演奏に固執するタイプ。悪く言えば未知の音楽(リズム)に対し、それを受け入れるだけの柔軟な発想と許容量を持ちあわせていない。セッションをやっていてもオイラの投げたリズムを受けとめるでなく投げ返すでもなく、自分のリズムをキープするだけ。まるでリズムボックスとでも演っているようで、セッションには不向きなタイプだ。
もうひとつはジャズ的なアプローチに対し、それを摂取し消化して吸収したものに自分の味付けをして投げ返してくるタイプ。まるでジャズという、否ジャズ云々以前の音楽(我々の場合リズム)に於ける対話とバトル。ここで具体的に例えて言えば、前記の のリズムとノリから のリズムとノリに自由に往(い)ったり復(き)たりしながら(これはリンガラ・ポップスなどのアフリカン・ミュージックにはしばしば見られる)、さらに3拍フレーズやアクセントの移行などのスパイスをじゃんじゃん加えていく。これで相手とのキャッチボールが上手くからオモシロイ。ドラマーとして大冥利に尽きる瞬間である。
後者は所謂(いわゆる)進化する遺伝子を持ったドラマーということになろう。進化とは、こうありたいと願うドラマーたちの向上心と探求心の賜物に他ならない。かつて爬虫類たちの一部は、空を飛びたいと願い翼を得た。オイラたちが生きてる間には背中に翼は生えてはこないが、2本のバチを翼に変えることはできる。夢を持ち続け努力することで、心はいつでも世界に翔けるからだ。
※オイラのグループは10月にロシアに旅立つ。 夢を持ち続ける者に、翼はいつでも用意されているのだ。
ROUND-10
民族とリズムの相関関係についての一考察
<万物と伴たらざるもの己の中にあるか>
炎天下のンバンビレ村で、連日のドラムセッションとドラム道場を演(や)っていたオイラは、少年たちのドラムセンスの良さに、はっきり言って兜(かぶと)を脱いだ。埼玉でやっていた闘魂ドラム道場の門下生と、ウガンダの門下生との根本的な相違は何か?
埼玉の門下生に「何でもいいから叩いてみな」と言うと、殆ど10人が10人とも判で押したように、巷に溢れているありふれたリズムを叩く。そんな時、師範であるオイラはコメカミのあたりが怒りでプルプル震えてくる。「あほんだらーっ! オマエらの存在理由はいったなんなんだ。みながみな同じリズムを叩いてどーする!」と一喝する。
というのもオイラの好きな言葉に「万物と伴(とも)たらざるもの己の中に存(あ)るか」というのがある。この大宇宙の万物に協調しないか、それを否定するに足りる自分だけの強烈な技を持ち合わせているか、とオイラは解釈している。どいつもこいつも4分の4拍子、おまけに四角い音符のオンパレードで、3連符なんざ全く出てこない。それに3拍子だって5拍子だって6拍子だってあんだョ。 門下生に「じゃあそのリズムを3拍子で叩いてみな」と言うと、金縛りにあったように動けない。「アホーッ!だからオメーらは音楽を演ってんじゃねーんだよ、音楽を叩かにゃあ、音楽を!」と、悪態のひとつもつきたくなるのだ。 それに比べてウガンダの子供たち---。
生まれて初めてドラムの前に座るというのに、両手に持ったバチでハイハットを3連符で叩き始めた。しかも多少パラディドゥルも入っている。ぎこちないが、そのままタムに移動もやっちまう。これでもうギャフン!ときた。埼玉では「3連符とバスドラを制するものは世界を制する」と言って、手間暇かけて教えていたのに・・・・。
<悟空の3連符的ココロ>
そもそも3連符とか3拍子とかいうのはいったいなんやろ? オイラもようは知らんが、これは人間の身体の造りだとか民族の生活習慣とかに関係があるように思う。
人間の手足は2本づつ、目も耳も鼻の穴も眉毛も乳房も2つづつ。歩くときは2拍子で歩く。どうも2という数字は人間にとって最も都合のいい造りらしく、からだの器官で3個あるものはない。 ものの本によると日本の民謡の中に(伝統音楽)3拍子は2~3曲しか無いらしい。それも北九州に集中しているから、朝鮮からの渡来人が歌ったらしいということである。お隣の韓国には4分の3拍子から8分の6拍子、8分の9拍子や8分の12拍子が多々あるというのに、なんで日本や東南アジア諸国には少ないのか? 人の話によると騎馬民族3拍子説がある。なんでも馬の走るタイミング(スピード)によって、(馬の)前足が着地し、次に後ろ足(の着地)、んでもって人の座っている鞍がポンと跳ね上がる---この一連の動作が3拍子になるというのだ。そうなると日本の騎馬武者が3拍子を歌わず、ウエスタンに4分の2拍子が多いのはなんで? と反論されそうだが、民族の歴史は数千年単位のもの、国の歴史なんてのはせいぜい百年単位の通過点でしかない。 それでは馬に乗らないアフリカ人がなぜ3連符を多用するのか? 諸君はTVの番組か何かで、アフリカの田舎の杵(きね)つ き作業を見たことがあるだろう。食料のキャッサバやとうろこしを粉にする作業なのだが、臼(うす)の回りに何人の女たちが杵をついているか観察したことがあるだろうか? 1人でも2人でも出来るが、家族が多いため多くは3人でやっている。4人では窮屈でやりにくい。したがって3人でやるのが日常的な習慣なのだが、歌でも歌えば伴奏はおのずから3連符のノリになってしまうのである。以上は オイラのオリジナルの説だが、学者センセイたちをも納得させられるものと自負している。
<生活に密着したリズム>
ンバンビレ村で日常使われているリズムを採取したので以下に記す。
・エマージェンシー
かつて侵入者に対して使われたらしい。現在も緊急で使うことがあるという。
PCで書き込めないのでゴメンナサイ
・もうひとつのエマージェンシー
・教会(プロテスタント)のサンデーサービスの時に叩く
・教会(カトリック)のサンデーサービス
・結婚式
・授業開始のサイン
・集合(学校で)のサイン
・授業終了のサイン
・昼食(学校で)のサイン
昼飯のマトーケを食うぞという意味らしい
クリマトーケー クリマトーケー ナーカジャンジャイロ クリマトーケー
<ついに完成! 臼(USU)ドラム>
数日前、とうとう20”(インチ)のバスドラムが完成した。ジャングルで大木を切り倒して中をくりぬき、乾燥させること約1年、TAMAの金具類を取り付けて楽器として生まれ変わった。これまで12”&13”のタムと14”のバスタムは仕上げ済みで、既にライブで使っている。オイラはこのドラムにニックネームをつけた。その名は「臼(USU)」。バスドラなどは肉厚が40ミリ以上あり、見た目にもモチをつく臼のようだ。誌上公開近し。乞う!ご期待!
※写真説明
木に吊るした車のホイール。これを叩いて授業開始や昼メシを知らせる。後ろの建物は小学校.。

ROUND-11
無農薬ドラムの製作
<足の裏が動物園>
オイラはウガンダでドラム村に長期滞在し、連日ドラムセッションで狂喜し、ダンスセッションで乱舞していたのだが、あろうことか実は足にダニを飼っていた。ふだん素足かゴムゾーリで生活していたのだが、あるとき足に「魚の目」状のおできを発見した。別に気にとめず放っておいたら、だんだん大きくなって中で虫が動き始めた。仕方がないので煙草の火で焼き殺し、ナイフでほじくり出した。これが1カ所だけでなく足の裏や爪の間に幾つも出来たのだから堪らない。連日足のウラに穴を空けるハメになってしまったのである。

畳2枚分の牛革を天日で干す
<道端が乾燥室>
ヌンチャクのトレーニング、水汲み、飯炊き、ドラムセッション、ディスコダンスを終え、午睡から覚めるとドラム工房に向かう。村のメインストリートの脇にはいつでも、牛の生皮を剥がしたのを数枚天日で干っ放しにしている。生皮はカンパラに近い町の屠殺場で手に入れるのであるが、その1枚の大きさは畳2枚近くもある。四角いその皮の四辺には、天日で皮が縮まないように数十本の杭が打ち込んである。そばに立つと生臭さもさることながら、生皮に群がったハエの大群には閉口する。ハエとて死んだ生皮より生きた生皮がいいに決まっている。オイラの顔といわず手足といわずハエにたかられてしまうのでサッサと退散する。この皮はときどき皮の内側に付いている柔らかい肉をヘラ状の物で削り取るだけで、一度干したら3~4日間干しっ放し。多少の雨も何のその、それ以上に日照のパワーが強烈なため、パリッパリに乾いてしまうのだ。これは後でドラムのヘッドにしたり、カバーに使ったり、細く長く裁断してチューーニング用のロープとして使うのだ。
<悟空は木ィを切ィるゥ~♪>

これがドラムになる木だ
何といっても大変なのは、ボディに使うマホガニーの大木の切り出しである。水筒がわりにシュガーケーン(さとうきび)を1本と、弁当がわりのバナナを携えてジャングルに入る。頭蓋骨を叩き割られるほどの炎天下とは違い、ジャングルの中は比較的涼しい。だが湿度は高く汗が流れ続けるため、オイラの皮膚は両生類のように湿ったまんまだ。そんななか事前に目をつけておいた大木の下に陣取って、伐採の3点セットを用意する。斧と鋸、それとくり貫くもの(名前を知らない)だ。最初斧で切れ目を入れ木の倒れる方向を決定し、次に鋸で引き始める。
オイラは最初の一撃を入れる前に木に両手を合わせた。「ナニヤッテンノ?」友人の村人は不審そうに尋ねた。「だって長いこと生きてきたのに木に申し訳ないから・・・」そう言うと、「ノープロブレム、14インチくらいの木になるのに7~8年もかからない。20インチほどでも10年と少しさ。1本の木から大小100以上のタイコが作れるんだし、それ以上の人々がタイコでハッピーになれるんだから木も幸せなんだョ」
ナルホド・・・そういうことか。今日本で流行りコトバの自然破壊のことも多少気になったが、電気もガスも水道も無いこの村では生活騒音そのものが皆無である。トイレットペーパーの代わりに木の葉を使い、空きビンでさえ何かの容器に役立て、古タイヤでゾーリを作り、車のホイール・カバーでナベさえ作ってしまう。ここで「自然破壊」などと喧伝したところで、それは一部の先進国のエゴにしか聞こえまい。 汗にたかってくる無数のブヨを追い払いながら切り倒した大木も、その日はそのままにして帰る。このあたりの作業は「日」の単位では無く、「週」単位や「月」単位になるように時間の目盛りを切り替えねばならない。何故ならチェーンソーや電気カンナがあるわけでもなく、歯っかけのオンボロ鋸や手斧で、大木を寸断していくのだから。 タイコの縦の長さに切られた木は(木を正確に直角に裁断することは困難を極める)、水気を多く含み柔らかいうちにその場で中をくりぬく。くりぬくと一言で言うものの、太い部分では楽に1~2日要するし手にはマメが出来てしまう。くりぬいた木は交代で持ちながら、ジャングルの入り口に停めてある自転車まで運び、荷台にくくりつけて ケモノ道を工房まで運ぶのだ。まるで炎天下でエサを運ぶアリさん状態なのである。
<無農薬ドラムの製作>
工房に運ばれた木はここでトラディショナルドラムの型(逆さ台形)に削られ、内側も外形に沿って削っていく。木の部分によっては虫が寄生していて直径1~2 の穴があいている。この虫を除去するために、牛の生糞(出たてのホヤホヤ)を塗りたくってカラカラに乾燥するまで暫く放置しておく。乾燥したら斧で薄く削り取ってしまえばOK。きょうび無農薬野菜ブームであるが、虫付きの野菜は虫が食うほど美味しいという解釈もある。ドラムとて然り。美味しいドラムの材料は虫にさえ分かるのである。


これは中サイズの村のドラム
こっちがスネア・ドラムの原材料
そうだ! オイシイ材料ならいっちょスネアドラムを作っちまおうかナ。んなら手始めに14×5インチのスネアからだ。15インチほどの幹を5インチほどの長さに切って、見よう見まねで中をくりぬいた。当然コンパスなどは無い。もとより中をくりぬいてあるので、あっても使えない。14インチのヘッドも持合せが無い。布製のメージャーを何度も当てながら目測で外側を円形に削り、ひび割れを恐れて肉厚は1インチ以上にした。 陰干しにすること1週間以上。工房のドラムはヒビ割れ防止に、まず陰干しを数日して日干しを数日するが、オイラのスネアは万が一のヒビ割れを警戒して陰干しだけにした。案の定ヒビ割れの予兆も無く、気を良くしたオイラは4ケのスネア用くりぬき胴を作ってしまったのだ。もちろんこれだけ作るのに1月以上は要した。オイラの手の皮が超人的に厚くなったのは言うまでもない。にもかかわらず更に12、13、14インチのタム、20インチのバスドラの製作に着手することになるのだ。
つづく・・・
ROUND-12
《チャンネル1》
<ドラム工房の光景>
ウガンダのンパンビレ村(通称ドラム村)のドラム工房では、連日若者たちが集まってドラム作りに励んでいた。総じ
て所帯持ちは自宅でドラムを製作し、独身者や若者たちはここに集まる。というのも少年たちは年長者たちにドラム作り方を教わるためでもあり、ここは月謝のいらないドラム製作スクールという意味合いも兼ねているからである。先輩たちは口径が18インチほどの大型のドラムを作り、少年たちは直径が数インチの土産物やアクセサリーに使う小型のドラム作りから始めていく。一通りの作り方をマスターした青年の中には蛇の皮を使った大型の円筒型のドラムを作る者もいる。これも基本的な作り方は他のドラムと同じだが、口径が11インチ程なのに比べ、深さが1メートルほどもあるので、くり貫くのに手間がかかってしまう。 因(ちなみ)にこの工房での収入は、給与制でも出来高制でも無く、「完全売れ高制」である。当然出来のいい作品は高く売れるし、粗悪なものは売れ残る。この界隈ではオイラの師匠、ムゼー・ガイラ氏(前出)の作品が一番評判がいい。だから彼は3人の奥さんを持てるし、ボロボロだが日本製のバイクにも乗れるのだ。
さて、仲間の一人が立ち上がってトイレに行くと言いい、その辺に有る立ち木の葉っぱを1枚だけちぎると、「ニヤリ」と笑って小屋に入った。枯れ枝で囲っただけのそこから、彼の黒光りする筋肉質の臀部が、妙に艶かしく見え隠れしていた。かつてオイラは中国・チベットへのドラム旅で則所(ツォーソー)に泣かされたことがある。誰にも見せたことの無いオイラの桃尻を、公衆の面前に晒すことに処女のような羞恥心を抱いたものだ。<牛皮製N0なめし捻じり紐の製作>閑話休題、牛の生皮の日干しは前回述べたが、ここには大蛇の皮もある(写真)。オイラのゴムゾーリのサイズが27センチあるから皮の幅はその倍の54センチとみて、太さが18センチもある大蛇が個の辺りにいるということになる。長さは正式には計ってないが、伸ばしてみたら途中で嫌になったくらいだから10メートル近くはあるのだろう。くわばらくわばら。 大蛇の皮は打面に使用するだけだが、牛皮は打面とタイコ全体を覆うためにも用いられる。その打面と覆いを連結し、チューニングを施すために使用されるのが牛皮のヒモだ。ドラム作りの工程に欠かせない のが、名付けて「牛皮製NOなめし捻じり紐」作りである。 乾燥させた牛皮を長さ数十センチの楕円形に切り取り、それを5ミリほどの幅で外側からヒモ状になるようにナイフで切り取っていくのだ。この作業はテクニックを要するので中堅の青年の仕事である。これで10~20メートルのヒモが出来ると、見習いの少年が水に漬けて柔らかく戻し、片方の端を立ち木にくくりつけると捻じりながらこよりにして、物干しのヒモのようにあっちこっちに渡して再び天日に晒して乾燥させるのだ。捻ってこよりにするには理由がある。まず引っ張り強度が増す。次に打面と覆い面を連結するにあたり、ヒモが捻じれてることによって緩みが生じない。ということはチューニングの作業も容易になるということになる。

これがその辺にいる大蛇の皮とヘビ皮ドラム。オイラのゴムゾーリと比較するとその大きさが判る。
《チャンネル2》
<ウガンダ製TAMA悟空ドラムの製作>
オイラはジャングルからやっとの思いで切り出してきたマホガニーの大木を切断してくり貫き、14×5インチ(ちゃんとした物差しが無いので、あくまでアバウトなサイズ)のスネア用の胴を完成させた。肉厚は1インチはある。正確な真円では無い。コンパスなどという文明の利器が無いのだ。いやそれ以前にジャングルからの担ぎ出しが重いので、先に内側をくり貫いてしまうため中心点を選べないのだ。多少の楕円ならまだいい。外形が歪(いびつ)なのが気になる。悪く言えばジャガイモの断面みたいでイヤだ。
それでも1月の間に4ケも作るとそれなりに上手くなってくる。蛇皮の円筒型ドラムに付けるデザインを真似て、やけ火箸で胴体にデザインを施したりもした。最初に作ったスネアの胴にひび割れが生じないのを確認すると、12・13・14インチも作ってしまった。だいたい1ケ作るのが1週間ほどだ。12と13インチはヘッドを持っていたので円を描けたのだが、出来上がりを真横から見るとボディーが膨らんでいて、和大鼓のような形になっていた。14×14インチのフロアータムには参った。だいたい斧と鋸とくり貫くものだけで正確に作れるはずが無い。悲しいかな真横から見ると、平行四辺形になっている。中身も平行四辺形にくり貫いているのだから矯正は難しい。「ええい!ままよ、世の中に平行四辺形のフロアータムがあったっていいじゃないか」と、このまま使うことにした。

スネアー・タムタム・バスタムのくり貫き胴が完成!残るは…
スネアを4ケ作り、12・13のタムと14のフロアータムを作ってしまえば、「次に欲しいものは?」と問えば「大口径くり貫きウガンダ製TAMA悟空バスドラ!」と大合唱が聞こえて来ようというものだ。オイラはそれを作るべく、村人や仲間達に極太のマホガニーを探してくれるよう頼んで回っていた。
<くり貫くのが好きだねェ>
先日、六本木のライブハウスで小山彰太氏と話した。20年ほど前、新宿のライブハウスに通っては氏のドラミングを最前列にいてコピーしていた話をし、ウガンダのくり貫きドラムの話を熱っぽく語った。彼は深く頷くと、さも思慮深げに言った。「40過ぎてイイのは鳥だけじゃない。ドラマーだってそうさ」「えっ、どーしてですか?」「だってシジュウカラって言うだろ」「・・・・」「それにしてもくり貫くのが好きだねェ」
20年前は彼から学び、15年前は彼に並び、10年前は彼を追い越し、5年前は引き離したつもりになっていた。ところがその日の氏のドラミングは、オイラの遙か前方を走っていた・・・・。嗚々、小山センセイ、ス・テ・キ・・・
つづく…
ROUND-13
<ロシアンコンサート>
オイラのバンド「のなか悟空&人間国宝」、通称「人国(ジンコク)」はロシアのモスクワとサンクトペテルブルグに演奏旅行に行ってきた。今回のイベントでは、日本・ロシア・ドイツ・フィンランド・スイスなどの国々から、超有名らしい(というのもオイラは自分以外のプレヤーの事を殆んど知らないのだ)ミュージシャンが集まった。僅か1週間に4カ所、延べ数千人の前で叩いちゃったのだからギャラの割には(貨幣経済崩壊寸前のロシアのことだからギャラは押して知るべし)、スッゴイ仕事をしたことになる。
だいたい「ジンコク」の観客動員の数はその少なさで右に出るバンドはあるまい。というのもオイラ自身がライブの日程を時々忘れてしまうことと、弟子たちにも教えないし情報誌にも出さない、おまけにフラッと海外にドラム放浪に出かけてしまう。それだけに数少ないファンもタイヘンだ。不思議なことにどこでどう見つけたのか、チャンとライブハウスに現れるのを見て、「どうして見っかっちゃったのかなァ?」と逆にこちらから聞いてしまったりもするのだ。しかもわざわざ北海道から飛行機で来たり、名古屋や京都から新幹線で来たりと、超マニアックで変わった人が多い。愛しくて掻き抱きたい衝動に駆られるが、どいつもこいつも体育会系のオッサンか、盛りを過ぎたオネエサンだったりするから情けない。
<手品のような職人技>
さてンパンビレ村のトラディショナルドラムの製作のだが、逆さ台形のくり貫き大型ドラムにいよいよ牛の生皮を被せる段階に突入する。パリッパリッに乾燥させた生皮を水に漬けて柔らかくし、打面用に大まかな円形に切る。更にドラムの底から包み込むように使用するカバー用の生皮も、柔らかくして大まかに円形に切る。それを上下から皮ヒモで連結する。早い話がドラムの木肌を露(あらわ)にせず、処女のように慎み深く覆い隠してしまおうという寸法である。その理由は定かではないが、察するに虫除けとルックス、それと常に地面に置いて叩くので底面の保護などがあるのだろう。
この上下の生皮を連結する頃がドラム作りの佳境に達する。考えてもみよ、筒形の台形ドラムを大まかな円形の皮で上下から包むのである。打面はまだいいとして、底面から包み込む皮にシワが寄ってしまうのは物理的に明白なはずだ。連結の工程では山脈状のシワが底部から放射状に十数本伸びていたものが、出来上がってしまうと殆ど目立たなくなってしまった。「あれっ? どーなってんの?」とキツネにつままれたようになってしまが、観察の結果そのナゾが解けた。秘密は低部から包み込む皮の形にあった。オイラが大まかな円形と思い込んだのは、実は大まかな星型だったことである。これを上からの引っ張り具合を調整しながら連結していけば、塩梅(あんばい)よくシワが消せるという仕掛けだったのだ。これを超人的な職人技でやれば、生皮が乾燥した後はシワのシの字もなくなってしまうのである。

ドラムの底部を牛皮で覆う。これが見事な職人技だ。
ちなみにこのドラムは低部を覆っているうえに地面に置いて演奏するため、低部の共鳴はいっさい当てにしない。なめしていない牛皮の厚みと、ボディーの厚さ(約1インチ)、口径(約17~21インチ)と容積の大きさによって、大海のうねりのようなゆったりとした重低音を叩き出す。演奏はバチを使用せず掌だけで行なう。この型でサイズが約11~14インチになると、皮はヤギの皮を用いる。打面の皮は毛を付けたままのものと、ナイフで削り取ってしまったものと半々ある。演奏は掌または2本のバチを使用する。このほかサイズは10インチ以下2インチ程のものが多々あるが、これらは置き物やアクセサリー等の土産物用にされる。
<ウガンダ製USU(臼)状バスドラムの製作>
マホガニーの大木をくり貫いた14インチのスネアーを4ケと12と13インチのタムを2ケ、14インチのフロアータムを拙くとも果敢にも作ってしまったオイラが、次に欲しくなるのはバスドラムに決まっている。どうせなら和太鼓に勝るほどの大口径のモンスターが欲しい。それを日本に送り、ザイールのサンダ・ーストーム(雷鳴)に勝るとも劣らぬ暴力的な重低音を叩き出して、観客の何人かをショック死させてみたいものだ。
そのためにも完成させた暁には日本への発送を考えて、カンパラのGPO(中央郵便局)へ1日仕事で問い合わせに行ってみた。係員は「コレクライマデナラOK」と両手でサイズを示したが、正式な規定は知らないと言う。ただ惜しむらくは18インチくらいまでが限度で、それ以上は送れないらしい。仕方なくモンスターは諦め、20インチくらいのバスドラムの製作をすることにした。 20インチとは言っても木の太さが20インチではダメだ。回りの皮を剥いだり円形に削ったりで、せめて24インチ程なければなるまい。こうなるとタイヘンなのがまず大木捜し、次に切り出し作業、そしてくり貫き作業と、ジャングルからの運び出しである。それこれもみ~んなドラム大明神様のためと諦め、半月ほどかけてやり遂げてやっと工房まで運び込んだ。20インチを真円に近く削り(帰国してヘッドを当ててみたらスカスカで19インチくらいしかなかった!)、深さを16インチにし、厚さを1インチほどにした。最後に火箸で模様を入れて遂に仕上げてしまったのである。

バスドラム用のくり貫き胴が完成。首から下げているのはナイフだが,どこか浮かない表情……。
写真を見てほしい。これはカンパラの安宿で完成したバスドラを手に得意満面になっているオイラである。首からナイフを下げて一見恐いものナシの勇者に見えるが、心なしか哀愁が漂っている。詳しいことは次回に述べるが、ウガンダの郵便&交通事情により、せっかく作ったドラム類を日本に送れず安宿で足止めをくっている―――の図なのである・・・・。
つづく
ROUND-14
<ロシアンコンサート>
オイラのバンド、「人間国宝」のロシア・ツアーについて前回少しだけ触れたが、バンド名がどのように紹介されたかというと、英訳で「The human treasures(人間の宝)」となる。それがいかほどの価値があるのか、百見は一聞にしかず(百聞は一見にしかずの逆)、ロシア人にとって前代未聞の爆裂狂乱パワーによる、「燕返し奏法」や「千手観音奏法」、更に「バスドラ・マシンガン奏法」を交えた土方ジャズ飯場コンサートは、彼らの感性に油を注ぎ火炎放射器を吹きつけたかのようだった。数千人の観客による阿鼻叫喚さながらの歓声の中から、「サムライ!」だとか「ハラキリ!」だとかいう掛け声があちこちからあがった。因縁浅からぬ近くて遠い国ロシア・・・二度にわたる大戦の経緯のある国民からの声援というものに、複雑な感懐を覚えながらの悟空ドラミングであった・・・。
<ウガンダの郵便事情>
さて、話は極寒のロシアからアフリカ大陸は赤道直下の国、ウガンダのカンパラ近郊のドラム村に移る。
ある日、ファクスを日本に送りたくてカンパラのGPO(中央郵便局)まで行くことにした。それにはドラム村を通る乗り合いのライトバンか、通りすがりのトラックに便乗すればいい。とはいえ乗り合いのライトバンがいつ来るのか、通りすがりのトラックがいつ通りすがるのかは神のみぞ知る。乗物は時刻表で運行しているわけではない。運が悪ければ炎天下で惚けたように立ち尽くしていなければならない。小一時間も待ってやっと車が来ても、体臭のきつい現地人の間でもみくちゃにされるか、尾低骨を床に叩きつけられながらのひと時である。終点に到着してもGPOまでは群れのように無秩序な人波を掻き分けながら、登山道のような上り坂を30分くらいは歩く。
GPOに着くとまず1番窓口(総合案内)に行って、ファックスを送りたい旨を伝える。すると「13番窓口へ行ってテレホンカードを買え」と言う。言われた通り13番窓口へ行くと、食事時でもないのに窓口に衝立を立てて弁当を掻き込んでいる。それでも急いでいるオイラは「日本へファックスを送りたいからテレホンカードをくれ」と言うと、迷惑そうな顔を露にして「ここでは売ってないから1番窓口で聞いてくれ」と言う。再び1番窓口へ戻って最初の質問をすると、「じゃあ2番窓口へ行け」と言う。言われた通り2番窓口へ行くと申し込み用紙を書かされ、「36番窓口へ行って支払いを済ませろ」という。通信時間が何分かかるか、もしかすると不通になる可能性もあるのにと不安になりながらも36番で支払いを済ませる。支払済のレシートと申し込み用紙を持って再び2番窓口に顔を出す。すると「暫く待て」と言う。どれくらい待つのか尋ねると、申し込み用紙の束を見せ「only 2hours」と投げやりな返事があった。

GPOの近くのメインストリート。道路の真中で身障者が喜捨をねだる。それでも12年前と違いウガンダは飛躍的に発展した。以前は両足を切断された人たちが,這っていたのをよく見かけたものだ。

同じくメイン・ストリートで盲目のオヤジのストリート演奏。氏言わく「毎日ここでコンサートをしているのサ」。親父の両肩に生活と哀愁が重苦しく乗っかっていた。それでも道ゆく人々は一顧だにしない。なんだか自分とダブって見えた。
総合案内の窓口はあってもいいとして、ファックスを送る窓口で支払いをしたなら合理的だと思うのだが・・・。いや、むしろウガンダにファックスの有ることだけでも救いと思うべきか?
ある別の機会に完成したスネアーとタムの胴を日本へ送ろうとGPOへやってきた。ところが梱包するダンボール箱が無い。ロープが無い。ガムテープが無い。宛名を書くマジックも無い。仕方なく数日は安宿を借りてドラム類を置き、荷造り用品を揃えることにした。そもそもダンボール自体を見かけないものだから、探して歩くのも体力勝負だ。やっと探し当てたところで新品は無く、路上で商品?が有るときだけ商いをしている中古ダンボール屋のオヤジと、喧々囂々の値段交渉が始まるのである。ガムテープは散々探したが見つからずビニールテープで代用し、ロープは適当な長さのものが無く、数十メートルもあるものを一巻も買った。兎に角ここではだいたい一つの物捜しに1日かかると思えば間違いない。
さてさて、やっとの思いで荷造りを終え、空っぽのキャスター付きバスドラのケースをリヤカー代わりにしてGPOまでの坂道を上った(写真はGPOの帰り、ウガンダの新聞にフォーカスされたものである)。国際荷物係のマダムたちは、お茶菓子を飲み食いしながら井戸端会議の真っ最中であったが、荷物用の書類に記入し税関のマダムに荷物の中身を見せる。マダムはいかめしい表情で内容物と書類を見比べると、「ワタシがこの印を押さないとジャパンへは送れ無いのよ」といった高慢極まる態度で「ドン!」とスタンプを押す。

輸出許可書にスタンプをもらうと、次は梱包である。ロープを職人並の手際の良さでテキパキと荷物に掛けていくと、マダムたちはオイラの仕事の艶やかさに感嘆の声を上げる。こういう時に幾多のバイトで培った底力がものを言う。送料は重量で決まるのだが、料金は全部切手をダンボールに貼るようになっている。ここでオバサンたちに一言申し上げたい。「切手を探すな!」。切手を値段別に分類してあるのは郵便局では当たり前のことだが、ここではチト違う。写真ブックのような分厚い本に、切手を値段別にも分類せずデタラメに挟んでいるものだから、探すのに手間取る。しかも最初から順番にめくるわけでもなく、鼻歌交じりに適当にこっちを広げあっちを広げしているものだから、そこそこの時間がかかってしまう。(まったくなァ~、値段別に分類して分類シールでも付けときゃいいものを・・・)。見兼ねたオイラは悪態の一つもつきたくなった。「ヘイ、マダム、ユーの仕事の半分は切手捜しだねェ」。マダムは何かを頬張りながら屈託なく笑った。皮肉を皮肉とも感じず、合理性とは疎遠の、むしろ対極にあるおおらかな民族なのである。
荷造りも終え、切手も貼り、さてさてこれで一段落かと思いきや、マダムの口から意外なコトバが飛び出した。「ヘイ、ミスター、ウガンダの汽車はもう何か月もストライキで動いてへんのやけど、荷物どないします?」。げっ!そ、そりゃーないだろーっ!!
つづく・・・
ROUND-15
<土壇場の落とし穴>
舞台は今話題の「ウガンダ」。
少年ゲリラ、殺人、強姦、エイズなどがテレビで取り沙汰されている。こともあろうにドラムバカのオイラは、そこで長期単身自費ドラム修業に明け暮れ、やっとの思いで「マホガニーくり貫きドラム」を完成させたのである。
さて、やっとこさ完成させたドラムも、GPOで送る段になってタイヘンなことを聞いた。「ヘイミスター、ウガンダの汽車はストライキでもう何か月も動いてへんのやけど、どないします?」「ゲッ! そ、そりゃーないだろーっ!」。そういえばケニヤからの汽車はウガンダ国境が終点だし、どこかで横切った国鉄のレールもペンペン草に埋もれていたっけ。ことの真相を確かめるためにカンパラ駅に出向いていった。
閑散とした構内には人影もまばらで、プラットホームにはペンペン草がはえている。レールはまっ茶に錆びていて、いかにも長期間使われていないのが一目瞭然である。オイラはすがるように事務所のマダムに尋ねた(あろうことか、ここのオバさんも何か食っている)。「すみませーん、汽車はいつ頃動くんでしょうか?」「知らないねェ、ムシャムシャ」「そ、そんなせっしょうなァ、だいたいいつ頃かわかりまへんか?」「さあね、いまんとこ半年ほど動いてへんけど、あと1カ月か2カ月か半年か、全然見当がつかへんね。ムシャムシャ」。オバさんは威嚇するような目つきでオイラを見据えた。「・・・だめだコリャ」。
オイラは再びGPOに引き返して思案した。海の無い国ウガンダから、いつ動くか分からない汽車でケニヤに陸送し、船便で日本に送るべきか?それともDHL(国際航空便)で送るべきか? 船便が20Kgで5~6千円ほど、航空便では2~3万円はかかる。しかも荷物は3~4ケはあるのだ。1泊250円の宿に泊まり、1ケ30円のドリアン(日本では1万円前後する)を食べる生活者にとって、航空便は想像を絶する値段である。貨幣価値が日本の20分の1程になっているオイラにとって、数万円の送料は数十万円にも思えてしまう。

象印のウガンダマネー。これが60円ほどの価値がある。ということは600円に使えるのだ。ちなみにウガンダにはコインが無い。
いつ動くか分からない国鉄、それ故にGPOの倉庫に長期間保管していれば盗難の危険性も大きい。運良くケニヤのモンバサ港から出港したとしても、取り扱いの不備から折角作ったドラムが割れる可能性も大きい。おそらく無事我が家に到着するのは半分の確率だろう。にも拘らずケチなオイラは安くあがる船便を選んだ。残念ながら19インチのバスドラは、乾燥が不十分で結構な重量がある。ドラム村の若者に日本に発送するための要領を教え、梱包用具と送料を渡して十分乾燥させてから送ってくれるよう頼んだ。
<悟空を尋ねて三千里>
ウガンダを発った後、1ケ月程ナイロビに滞在し、孤児院などで2~3のコンサートをした。さらにドラムを担いでエジプトを徘徊した後、タイ東北部で出家遁世の日々を過した。帰国したのはドラム村を出て3ケ月の後。そして例の船便が我が家に届けられたのは、その3ケ月ほど後、つごう半年近くにも後になる。梱包した外装はボロボロに破れ、直方体であるはずの段ボール箱は、へたってジャガイモのようにデコボコになっていた。クッション代わりに入れていたドラム村製のシェーカーは幾つか壊れてはいたものの、「くり貫きドラム」は無傷で我が家に届けられたのである。スネアー胴4ケ、12インチタム、13インチタム、14インチフロアータム、どれもこれもがダンボールの中から逞しく我が家の狭い部屋の中へ這い出してきた。そのどれもがカンパラで送った時よりも更に乾燥して軽くなっている。その一つ一つを手に取り、女の柔肌を愛でるかのように愛撫した。「そうかァよしよし、おまえら到頭オレんちに来たかァ。ふーん、インド洋を渡ってねェ。えっ? 南シナ海も? そーかそーか」。アフリカ大陸からはるばる南国の風に吹か れて、埼玉の我が家に辿り着くにはさぞかし積る話もあろう。オイラは「くり貫きブラザーズ」を上座に据えると、飽きることなく眺めていた。
<読者の厚意>
「残るは19インチバスドラムの到着を待つのみか・・・」。その後、待てど暮らせど19インチは我が家に届かず殆ど諦めていた。そんな折、この連載を読んだ読者からドラム村へ行きたいという連絡が入った。オイラは電話でウガンダの交通事情などを話ながら、もし村にバスドラがまだ送られずにあったなら(発送を依頼した青年が送料を使い込むことは容易に想像できた)、お手数をかけるが送ってくれまいかと依頼した。案の定ドラムは村にそのまま有り、読者がDHLで我が家に送ってくれたのである。実に製作以来10ケ月が経過していた。おかげででようやく「くり貫きブラザーズ」のファミリーが全員揃い、いよいよ「TAMAウガンダ仕様マホガニー極厚くり貫きドラム」の製作に着手したのである。
<製作開始!>
バスドラとスネアーは難しそうなので後回し。まずは無難なところで12インチのタムを最初に手がけた。肉厚はどれも平均1インチ以上(1センチじゃないぞ!)はある。しかも均一ではない。それはそれで規格統一された機械で作るわけではなく、汗水たらして削ったものだからそれなりの味わいもあろう。敢えて不均一な肉厚はいじらないことにした。問題は「リム」だ。この形状によってヘッドの「鳴り」が根本的に変わってくる。悲しいかな大木を原始的なノコで切断したこの胴は、断面図の上下の辺が直線では無く、多少いびつであり湾曲している。これを修正しないことには、本当の意味でのドラム作りは始まらない。かと言ってここまで道具を使わず原始的な製法にこだわってきたオイラだ。こうなったらトコトン原始的な作り方に拘わることにした。
揃えた道具はサンドペーパー、包丁、彫刻刀、ニス、手動ドリル、定規だけ。金具類のフープ、船形、スナッピ等は全面的にTAMAに提供してもらった(オイラはかれこれ20年もモニターをしているのだ)。

ホントに手作りのドラムだ。電気工具はいっさい使ってない。
乞うご期待!次号でいよいよ神器、「くり貫きドラムセット」の完成だ。次号に於て遂に、「のなか悟空の世界を叩け」の連載のフィナーレか!?
ROUND-16
世界一のドラムセットの完成
<門外不出の秘法発見>
ウガンダで製作した「くり貫きブラザーズ」は、はるばるインド洋を越えて遂に我が家に到着した。全員がそろうのに実に10カ月を要したのである。オイラはこれらを「楽器」に仕上げるために、いよいよ金具アクセサリー類を取り付けるべく最終段階に入った。ジャングルでの大木選びから伐採・運び出しと、トコトン原始的な製法に拘わったオイラは、電動工具はいっさい使わず、彫刻刀、包丁、サンドペーパー、手動ドリル、三角定規だけでの作業を開始した。まずは12インチのタムから。一番の問題は上下のエッジをいかに平らにするかである。ナイロビ在住の石川晶氏(ROUND3出)のアドバイスでは、ガラス面などの平らな部分に何かの粉を薄く敷きつめ、その上にエッジの部分を被せるように置く。そうしてエッジの粉のついた部分だけをサンドペーパーなどで削っていくという方法らしい。これもいい方法だがプラスティックのヘッドを張るには更なるデリケートな作業を必要とする。幾つかのドラムメーカーにアドバイスを乞うたものの的確な回答は得られない。だが必用は発明の母という。多少の労力は要するものの、一銭もカネをかけず、完璧 な「まっ平らエッジ」を製作する術を考案したのである(拍手=これは画期的な特殊技術であるため読者といえども極秘である。食い物の差し入れと交換に教えるかも?)。
<11m余りも手作業で削る!?>
エッジをまっ平らにしてしまうと、次はエッジの「断面直角三角形削り」である。ご存じのようにエッジの断面を拡大すると鋭利な直角三角形になっている。現在は底辺が1インチの長方形であるから、包丁や彫刻刀を使って直角三角形に仕上げねばならない。いくらマホガニーの材質が柔らかいとはいえ、コツコツと削る作業は並の労力ではない。12″タムで、12″×3,14(円周率)×2(上下のエッジ)≒75インチも削らなければならない。これに13″と14″のタム、14″スネア、19″のバスドラム(これは暑さが2″近くもあるのだ)を総合計すると452インチ(1148cm)、実に11m余りも包丁と彫刻刀だけで削るのである。鳴呼、あたかも万里の頂上を建造するかの如き気の遠くなるような作業なのだ。1週間ほどかかってやっと12″タムの上下のエッジを三角に仕上げた。面の皮が薄いぶん掌の皮の厚いオイラは、過酷な作業にもめげずマメの出来る気配はなかった。
次は全面にサンドペーパーをかける作業。最初は目の荒いものを用い、仕上げは目の細かいものを使う。これは彫刻刀や包丁と違ってケガをする心配がないので、のんびりテレビでも見ながらやればいい。それが終わるとヒビ割れ防止のためと化粧のためのニス塗りだ。1年近く乾燥させた材料をこれ以上乾燥させないために、また日本特有の多湿の進入を防ぐためにもニスは3回塗ることにした。
<第一号の完成>
最後は舟形の取り付け作業だ。エッジが必ずしも真円では無く、横面が必ずしも長方形では無い。そのため舟型を取り付けるための穴もひとつひとつ測って開けなければならない。規格通りではない胴の形状に忠実に舟形を取り付けるということは、取り付けた後の舟形が必ずしも整然と並んでいるというわけではない。オイラの取り付け作業が下手だというわけでもなく、その太鼓の形状に即したその太鼓の音を最大限に引き出すための作業なのだ。早い話が、己のスタイルを最大限にかっこよく見せるためのオーダーメイド・スーツだと思えばいい。あふりかのみんげいかぐちょうのぼでぃーにとりつけたのは、TAMAのダイキャストフープにスタークラッシック用の舟形だ。パワーとアンティーックとエスニックが同居したこの「くり貫きブラザーズ」の高級感といったらタマラナイ。試しにスタンウェイやストラビバリウスの隣に置いたとしても、見劣りはすまい。ソナーやグレッチでは言わずもがな。
勢いづいたオイラはたて続けに13″タム、14″スネアー、14″フロアータム、19″バスドラムを作り上げた(といっつても数ヶ月要したが)。
<和太鼓に負けないドラム作り>
唐突だが、オイラは練習を屋外でしかしない。なぜなら太陽によってエネルギーが充電される、ソーラーパーワーのドラマーだからである。太陽によって充電された力を、大自然と民族に放電するのがオイラの仕事。チベットの太陽も、アマゾンの太陽も、ザイールの太陽も常にオイラの頭上にあった。ところでザイールのジャングルから聞こえてくる伝達用の太鼓は、数十キロメートルもの伝達能力があると聞く。日本の盆踊りの太鼓の音も、隣村から風に乗って伝ってくるのを聞いたことがある。果たしてオイラ達の叩くドラムセットに数キロ~数十キロもの伝達能力があるだろうか? かつて西荻窪のライブハウスで和太鼓奏者の林英哲氏とドラムバトルを演じたこともあるし、北海道の原野で和太鼓集団とセッションをしたこともある。果たしてその結果はどうだったのか? ここで客観的にドラムセットと和太鼓を聞き比べてみたとしよう。仮に両方の奏者が同じパワーで叩いていたとすると、10m離れた場所で聞くのと100m離れた場所で聞くのでは音はどう違うだろう?更に1Km離れたなら?結果は明白。悲しいかなどラマー諸君、我々西洋ドラム奏者は音を遠くまで伝達するという能力に於て、和 太鼓に一歩譲しかないのである。それは太鼓の径もさることながら、胴の厚みとヘッドの厚みに起因する。その先天的な弱点を克服するため、オイラは極厚の胴をもったドラムセットを作ったのである。
いよいよ次号がこの連載のフィナーレとなる。グレッチのドラムセットとオイラの作った「くり貫きブラザーズ」のどっちが「鳴る」か?詳細なレポートとともに結果を報告してエンディングとしよう。


これがスネアドラムの完成品とバスタムの完成品。画面が暗く、ピントも甘くて残念だ。
ROUND-17
<ファイナルステージ>
ドラマガの読者諸君、オイラの連載もいよいよ今回をもって終了する。ウガンダのドラム村のレポートを数回で報告するつもりが、ついつい乗りまくって17回もの長きに渡ってしまった。ドラムソロを4小節だけするつもりが、勢い余ってフルコーラス叩いてしまい、そのままフリーソロに突入してしまったような状況だ。
さて、前回はウガンダのドラム村で製作した「マホガニーの大木くり貫きブラザーズ」が、TAMAの極厚ダイキャストフープで武装し、スタークラッシックの舟形で装飾を施した。その艶姿(あですがた)を、スタンエェイやストラビバリウスにも勝るとも劣らず、パワーとエスニックとアンティークが同居した逸品だと紹介したが、肝心の「鳴り」はどうか?試しにグレッチやラディック、TAMAやパールと叩き比べてみた。
<治外法権のアフリカ象ドラムとは?>
*手前味噌証言・その① タムの場合
周知のようにグレッチのドラムは、ジャズドラマー達にとって神器と崇められるほど、ハイ・チューニングでの鳴りには定評がある。グレッチのリムの形状はポピュラーだが特殊合金を使用し、シエルは硬くて薄い。これが「鳴り」の基本かと思いきや、「くり貫きブラザーズ」はTAMAの極厚ダイキャストフープに、極厚1インチ(センチじゃないぜ)シエルである。なんと!対決の結果は「くり貫き」の大勝利!あのグレッチのタムでさえ補聴器をつけなければ聞こえないほどに小さく思えるのだ。もちろんこのテストには奏法も大きく関わってくる。オイラのように太陽に聞かせるつもりで「ブッ叩く」奏法でなければ、「くり貫き」を鳴らすことは出来まい。
*手前味噌証言・その② バスドラムの場合
我が人間国宝のライブでの話。その日は19″の「くり貫きバスドラム」を初めて使った。リハーサルでヒゴヒロシのエレキベースも近藤直司のサックスも小さくて聞こえない。それなのに彼らのボリュームはいつもより上がっていて既に限界らしい。ドラムは生音だがベースのスピーカーは棺桶のようにデカい。原因はバスドラムが「鳴り」過ぎて他の音をぜ~んぶ食っちまっていたのだ。これまで18″~26″の国内外の各種メーカーのバスドラを散々ブッ叩いてきたが、特に良く鳴るグレッチの18″やTAMAの22″クリスタルでもこのようなことは無かった。
*手前味噌証言・その③ スネアーの場合
「くり貫きスネアー」とラディックのメタルスネアーを叩き比べてみた。サイズはともに14″×5″だ。ラディックのメタルがよく鳴ることは周知の事実だ。ところがどうだ!このメタルスネアーうるさすぎて耳が痛い。「鳴る」というより「うるさく」、「うるさい」というより「やかましい」。音楽の「音」から最も距離を隔てた部分に位置する、例えて言えば「パニック状況に陥った女のヒステリー」と言う表現が最も似合う。思わずブン投げてしまいそうになったほどだ。
片やオイラの「くり・スネ」、世の中にこんな柔和なスネアーの音があったのかと耳を疑ってしまう。「真綿で首を絞める」という表現があるが、もし「真綿でスネアを叩く」とこんな音になるのだろう。柔らかい。とにもかくにも柔らかい。そして優しい。
どっこい、リムショット。これがたまらん。だてにTAMAの極厚ダイキャストフープを使っちゃいない。これに加えてスティックはTAMA特注の17ミリ径オークだ。ヒッコリーを使えば音はトコトン柔らかくなるのは請け合いだが、いかんせんよく折れる。オイラのリストの力とタイミングでリムショットをすれば、まるで「つらら」か「ダイコン」のように折れてしまう。不経済なのもさることながら、いま流行りの森林破壊にもなりかねない(笑)。
オークの既製品は15、5ミリまでしか作ってないが、1,5ミリの差は大きい。たったの1,5ミリ だが100mを10秒で走るか8,5秒で走るかくらいの大きな開きがある。この僅か1,5ミリの壁が記録的なサンダーストーム(雷音)を叩き出すのだ。極厚リムと極厚シエルと極太スティック、この三位一体のコンビネーションの音は、優しさと強さの両方を兼ね備えたゾウさんのような楽器なのである。
*他人味噌証言・その④
練馬にモリタ楽器というドラム専門の老舗がある。この店に2カ月ほど「くり・スネ」を置かせてもらって、客に自由に叩いてもらった。その感想を二代目モリタ氏に聞いた。FAXで送られてきた原文のままを紹介しよう。「まず体力のあるパワードラマーにお勧めで、全体的に太く重く迫力がある(皆は迫力のある音に驚いていた)。他には全く類の無い異質のスネアー。あまりにもど派手過ぎて、他メーカーのドラムと合わすと、無理あってセットのほうが負けてしまって勝負にならず、バランスが取れないので、同じ材質のセットを作るか、または単体(スネアーのみ)で使うことがいいと思いました」
どうだ!プロの評価がコレだ。まるで治外法権のアフリカ象なみの扱いではないか。作ったオイラもこの判定には鼻が高い。「くり・スネ」が1匹のアフリカ象なら「くり・タム」と「くり・バス」のフルセットは「アフリカ象の群れ」ということになる。


格調も高いバスドラムの完成品。ソナーやグレッチより鳴るぜ! タムタムの完成品は火箸でつけた模様がタマラナイ。
<エピローグ>
オイラのバンド「人間国宝」は5月にドイツのジャズ祭に招かれることが決まった。この「くり貫き」の群れを率い、ライブに来たドイツ人の聴覚に乱入し、世界観が変わるほどの感動を与えるのがオイラの夢だ。
諸君!連載のエンディングに美辞麗句は不要だ。とにかく起て!バチを握りしめろ!諸君の夢の実現のために!オイラはまたアフリカへ旅立つ!